 Music: やさしく愛して
Music: やさしく愛して
国立民族学博物館
オセアニア
2011.12.04

オセアニア 出典:ウィキペディア(以下、青字部分すべて) オセアニア( Oceania)は、六大州の一つ。大洋州とも。狭義には、ニュージーランドを含むポリネシア、ニューギニアを含むメラネシ ア、そしてミクロネシア全体を指す。広義にはオーストラリアとオーストラリア領のインド洋上の島も含む。また稀に、米・英・仏領以 外のオセアニアをアジアに含める場合もある。 六大州中最小の州であり、その小さな陸地面積のうちオーストラリア大陸が86%を占め、さらに島々の中で最も大きなニューギニア島 とニュージーランドを含めると98%にもなる。残りは、太平洋の中に点在する小さな島々であり、それがオセアニア(大洋の州)との 州名の由来にもなった。これらの諸島は陸地面積こそ小さいものの、マレー・ポリネシア系民族が独特の航海術によってすみずみまで植 民しており、独自の海洋文明を築いていた。ここでは広義のオセアニアを扱う。オセアニアの人口は、2000年の推計値で14,956,085人で ある。



<名 称> これらの3地域の名称は、ヨーロッパ人探検家たちによる命名が始まりである。1756年、フランス人探検家シャルル・ブロス(Charles Brosses)「多くの島々」を意味するギリシャ語の「ポリネシア」を太平洋全島々の総称として用いたのがはじまりである。その後、同じ くフランスの探検家デュモン=デュルヴィユ(J-S-C Dumont D'Urville)がオセアニア島嶼部を3地区に分けることを考えだし、1831年に パリの地理学会で公表した。現在は、この案を基本的に踏襲している。「メラネシア」はギリシャ語で「黒い島々」を意味し、「ミクロ ネシア」はギリシャ語で「小さな島々」を意味することから名づけられた。
オセアニアの位置。

<歴 史> ・先史時代 今から約5〜6万年前から 3万5000年前、東南アジア方面から現在のオーストラリアやニューギニアの内陸部や沿岸部へ住み始めたのは オーストラロ・メラネシア系(オーストラロイド)の人々であったといわれている。これらの人々は、このオセアニアに移住する前は、 東南アジアの島々や東アジア大陸に居住し、狩猟採集しながら暮らしていた。 ところで、約5〜3万年前は、更新世の最終氷期の時代であり、地球規模で気温がさがり、海面も現在の海面よりも最大で150メートル も下がり、島々は大陸とつながっていた。たとえば、ボルネオ島やジャワ島などはアジア大陸(スンダ陸棚)とオーストラリアやニュー ギニアは陸続き(サフル大陸)であった。しかし、この両者(スンダ陸棚とサフル大陸)はこの時代も海によって隔てられており、多く の島々が存在した。ウォーラシア海域と呼ばれ、最短でも直線で100キロメートルほど離れていた。

人々は海を渡り、各島へ移住していったのは約3万5000年前のことと言われる。これらのことを示す証拠として有袋類のクスクスや 黒曜石が多数出土している。しかし、ソロモン諸島より東への移住はこの時代でなく、はるか後の約3300年前にまで下がってくる。 やはりオーストロネシア語系の言語を持つモンゴロイド系の一群は、ラピタ人と呼ばれている。彼らはパプアニューギニアのビスマーク 諸島から東南方向に島伝いで移動しフィジーにたどり着いた。そこから南西方向(ヴァヌアツとニューカレドニア)と南東方向(トンガ とサモア)の二方向に分かれて遠くまで移動を続けた。こうしてトンガやサモアにたどりつたラピタ人は、そこで1000年ほど留まり今の ポリネシア文化の祖形を作り上げた。そして、ポリネシア人へと変容した。およそ2000年前に移動を再開し、1600年前ごろにはハワイ諸 島やイースター島まで到達していた。さらに、彼らポリネシア人は、800年前にはニュージーランドにたどり着いている。



当然といえば当然だが、漁具や船は発達している。 漁具はオセアニアにおける漁携技術の研究にとり重要な対象である。なかでも釣り針は、遺物として多く発見され、地域的な分布もひろ い。その型式の分布・年代関係の研究は、オセアニアの人びとによる海洋環境への適応過程や民族移動の歴史をしるうえで重要とされて きた。(略) 漁法を大まかに漁具の種類別に分類すると、釣り漁、筌漁、網漁、突き漁、追い込み漁、、採集、その他のようになる。このなかで釣り 漁の数がもっとも多く、体長10cmくらいのスズメダイのような小さな魚から、体長1m以上にも達する外洋性のマグロやサワラまでが対 象とされる。礁原での漁撈には、貝類、ウニなどの採集活動のほか、タコの突き漁、投網漁、ココヤシの葉製ロープをもちいた追い込み 漁などがある。リーフの前縁斜面で筌は、もぐりによる魚の突き漁・シャコガイの採集、底釣り漁、筌漁などがおこなわれる。外洋での 漁撈には、底釣り漁、流木漁、トビウオの松明漁、カッオ・マグロの引き釣り漁などがふくまれる。 「[ミクロネシアの筌漁] −漁具・漁法の生態学的研究− (国立民族学博物館第一研究部・秋道智彌)」より抜粋

ラピタ人 ラピタ人(英: Lapita)は、人類史上初めて遠洋航海を実践し、太平洋の島々に住み着いたと思われる民族。 1952年、ニューカレドニアで発見された土器が「ラピタ土器」と命名されたことから、この文化がラピタ文化と呼ばれるようになった。 ポリネシア文化の源流とする考えが有力である。「ラピタ」という名前自体は、ニューカレドニアの現地語 (Haveke language) で「穴 を掘ること」または「穴を掘った場所」を意味する「ハペタア (xapeta'a)」を、発掘した遺物のことと誤解して付けられた。この文化 が元々はなんと呼ばれていたのかは、現在まで明らかにされていない。 <歴 史> ラピタ土器の破片が、ソロモン諸島のネヌンボ遺跡 (Nenumbo site) でオークランド大学のロジャー・グリーン (Roger C. Green) らに よって1970年代に発掘された。破片幅は約8cmで、紀元前1000年ごろのものと見られている。ラピタ文化は今からおよそ3600年前にメラ ネシアで発生、高度な土器文化を持ちラピタ土器を残した。 ラピタ土器のうち古期のものは、紀元前1350年から同750年の間にビスマルク諸島で作られたものが見つかっている。その後紀元前250年 ごろまでに、次第に多様化した。バヌアツやニューカレドニアには、その地方独自の様式が見られる。メラネシアやパプアニューギニア のウンボイ島 (en) でも見つかっているが、それらが絶えた後もフィジーでは作られ続けた。 またラピタ土器は、ポリネシア西部では紀元前800年くらいからフィジー、サモア、トンガの一帯で作られはじめた。トンガからサモア へ、つまりポリネシアの東方にむかって植民によってラピタの文化が広がっていき、続いてマルケサス諸島、ソシエテ諸島、さらには ハワイ、イースター島、ニュージーランドへと伝わった。しかしラピタ土器はポリネシアのほとんどの地域で途絶えた。これは小さな島 などでは、土器を作るのに適した粘土が得られにくかったためと考えられる。 <遺 物> 土器は低い温度で焼いて作られており、貝殻や砂を混ぜて作られたものもある。多くは歯型の文様が付けられたが、これは樹皮布や入れ 墨などにも用いられていたと考えられている。ラピタ文化圏では文様のないもの、すなわち石製の鍬 (adze) などの人工遺物や、黒曜石、 チャートなどで作られた石器も見つかっている。 <経済活動> ブタ、イヌ、ニワトリなどの牧畜が行われていた。またイモや果実を収穫するための農業も行われており、主にヤムイモ、タロイモ、コ コナツ、バナナ、パンノキなどが栽培されていた。これに加えて漁業が行われ、黒曜石や石の鍬、その原料となる各種の石や貝殻などと の交換による遠距離交易が行われていた。 <風 習> ハヌアツ、エファテ島のテオウマ遺跡 (en) で2003年に見つかった古墳では、36体の遺体が25の墳墓または甕棺に埋葬されていた。遺体 はすべて頭部を欠いており、これは一度埋葬した後に、頭部だけを取り去り巻き貝で作った指輪と置き換えていたためであった。その頭 部は別に埋葬されており、埋葬されている老人の胸の上に3つの頭部が並べられていた墓が見つかっている。また見つかった甕棺の一つ には、4羽の鳥が中をのぞき込む造形が見られた。炭素年代測定により、墳墓の中の貝殻はおよそ紀元前1000年ごろのものとされている。 <植 民> ポリネシアの西部では、人々の住む村落は大きな島の海岸沿い、あるいは小さな島に作られた。これは、ニューギニアの海岸などではす でに住んでいた別の民族との衝突を避けるため、あるいはラピタ人にとって致命的な病気であったマラリアを媒介する蚊をさけるためで あったと考えられている。礁湖 (ラグーン) の上に作られた高床式の住居も見つかっている。ニューブリテン島では内陸部、黒曜石の産 地の近くに植民したのが分かっている。ポリネシア東部の島々では内陸部に、しばしば海岸から距離のある場所に入植していた。 ラピタ土器はビスマルク諸島からトンガにかけて見つかっているが、その東端はサモア、ウポル島のムリファヌア村 (en) である。ここ では4288個の土器片と2個の石の鍬が見つかっている。炭素年代測定により紀元前3000年のものと見られている。牧畜も、土器同様にオ セアニアの各地に広まっていった。ラピタ人、家畜、その移動についてきた他の生物 (おそらくナンヨウネズミなど) は、外来種として、 結果的に多くの移住先で飛べない鳥を始めとする固有種を絶滅させることになった。 <言 語> ラピタ人の言語は、オーストロネシア語族のオセアニア言語の元となった原オセアニア言語 (Proto-Oceanic) だったであろうと考えら れている。しかしこれまでに見つかっている考古学資料は言語に関するものが少なく、言語自体に関する資料は乏しい。 <ラピタ人の起源> ラピタ人のルーツは不明だが、台湾の土器との関連性が考えられている。ただしその間のインドネシア付近との関係はいまだに不明であ る。わずかに発見されている人骨から、人種的には現在のポリネシア人に似た大柄な人々だったらしいと言われている。 ラピタ人のルーツは不明だが、5000〜6000年前の台湾または中国南部のオーストロネシア人 (en) かもしれない、新石器時代に人口増加 により移住を余儀なくされ、東南アジア (台湾) から移動した (「ポリネシア特急」とも呼ばれる) のではないか、と考えられている。 台湾の赤い細長い陶板に似た特徴がポリネシアの甕棺にも見つかっており、言語学的にも対応が見つかっていることが、それを裏付けて いるとする。一部の研究者は、ラピタ人の移住は「トリプル I」に特徴づけられる、としている。それは、 intrusion - 新しい土地への侵入 innovation - 新しい技術の獲得 (アウトリガーカヌーなど) integration - すでにいる民族との統合 という3つの過程があることである、としている。現在はインドネシアやマレーシアではラピタ人に関するものは見つかっておらず、そ のためユーラシア大陸の民族とラピタ人を結びつける根拠はない。またそれとは別に、ビスマルク諸島では30,000年から35,000年前に人 が住んでいたことから、これがラピタ人のルーツである、とする意見もある。それによると、ポリネシア西部でのラピタ人の広まりは、 黒曜石の交易によるものであるとされている。


ヤップ島で使われた石の通貨。日常流通していたのではなく、結婚の持参金や土地の売買に使われたもののようだ。



イースター島 イースター島(英:Easter Island)はチリ領の太平洋上に位置する火山島。現地語名はラパ・ヌイ(ラパ・ヌイ語:Rapa Nui)。正式名 はパスクア島(スペイン語:Isla de Pascua)で、"Pascua"は復活祭(イースター)を意味する。日本では英称で呼ばれることが多い。 モアイの建つ島である。ポリネシア・トライアングルの東端に当たる。周囲には殆ど島らしい島が存在しない絶海の孤島である。「ラパ・ ヌイ」とはポリネシア系の先住民の言葉で「広い大地」(大きな端とも)という意味。かつては、テ・ピト・オ・ヘヌア(世界のへそ)、 マタ・キ・テ・ランギ(天を見る眼)などと呼ばれた。これらの名前は19世紀の後半に実際に島にたどりついたポリネシア人がつけたもの。 海底火山の噴火によって形成された島に、最初の移民が辿り着いたのは4世紀〜5世紀頃だとされている。この移民は、遥か昔に漢民族の南 下に伴ってインドシナ半島から押し出されたポリネシア人である。ポリネシア人の社会は、酋長を中心とする部族社会であり、酋長の権力 は絶対で、厳然たる階級制度によって成り立っている。部族社会を営むポリネシア人にとって、偉大なる祖先は崇拝の対象であり、神格化 された王や勇者達の霊を、部族の守り神として祀る習慣があった。タヒチでは、マラエと呼ばれる祭壇が作られ、木あるいは石を素材とす るシンボルが置かれた。イースター島でも、同様に行われていたと想像できる。化石や花粉の研究から、当時のラパ・ヌイは、世界でも有 数の巨大椰子が生い茂る、亜熱帯性雨林の島と考えられている。初期のヨーロッパ人来航者は、「ホトゥ・マトゥア」という首長が、2艘 の大きなカヌーで、ラパ・ヌイに入植したという伝説を採取している。 <モアイ像> 7世紀〜8世紀頃に、プラットホーム状に作られた石の祭壇(アフ)作りが始まり、遅くとも10世紀頃には、モアイも作られるようになった。 他のポリネシアの地域と違っていたのは、島が完全に孤立していて、外敵の脅威が全くなく、加工し易い軟らかな凝灰岩が、大量に存在し ていたことである。最初は1人の酋長の下、1つの部族として結束していたが、代を重ねる毎に有力者が分家し、部族の数は増えて行った。 島の到る所に、其々の部族の集落ができ祭壇が作られた。モアイは良く「海を背に立っている」と言われている。ただし正確には、集落を 守るように立っており、海沿いに建てられたモアイは海を背に、内陸部に建てられたモアイには、海を向いているのもある。祭壇の上に建 てられたモアイの中で、最大のものは高さ 7,8m、重さ80tもある。島最大のアフ・トンガリキには、高さ5mを超えるモアイが15体も並んで いる。 デザインも時代に連れ変化し、第一期のモアイは、人の姿に近いもので下半身も作られている。第二期のモアイは、下半身がなく細長い手 を、お腹の辺りで組んでいる。第三期のモアイは、頭上に赤色凝灰石で作られた、プカオ(ラパヌイ語で髭あるいは髪飾り)と呼ばれる、 飾りものが乗せてある。第四期のモアイは、全体的に長い顔、狭い額、長い鼻、くぼんだ眼窩、伸びた耳、尖った顎、一文字の口など、こ の頃に作られたモアイは、最もモアイらしさが強調されるようになった。18世紀になって西欧人が島に訪れるまで、島には鉄器や銅器は存 在せず、モアイは比較的に加工し易い凝灰岩を、玄武岩や黒曜石で作った石斧で刻み、10世紀〜17世紀まで、少なくとも800年は続いた。 当時作られたモアイや墳墓、石碑といった、考古学的に極めて重要な遺跡が数多く残されている。16世紀以降、モアイ(石像)は造られな くなり、その後は破壊されていった。この時期までが先史社会と考えてよく、ラパヌイ社会の転換期である。 平和の中でのモアイ作りは突然終息する。モアイを作り、運び、建てる為には大量の木材が必要で、大量伐採によって森が失われる(森を 破壊したのはネズミであるという説も存在する)。森を失った島からは肥えた土が海に流れ出し、土地が痩せ衰えた。そこに人口爆発が起 こり、当時の島には1万人を超える人々が暮らしていたとも一説では2万人が住んでいたともされる。僅か数十年の間に人口が4倍にも5倍に も膨れ上がった結果深刻な食糧不足に陥り、耕作地域や漁場を巡って部族間に武力闘争が生じるようになる。モアイは目に霊力(マナ)が 宿ると考えられていたため、相手の部族を攻撃する場合、守り神であるモアイをうつ伏せに倒し、目の部分を粉々に破壊した。その後モア イ倒し戦争は50年ほど続いた。森林伐採は結果として、家屋やカヌーなどのインフラ整備を不可能にし、ヨーロッパ人が到達したときは島 民の生活は石器時代と殆ど変わらないものになっていた。 1722年の復活祭の夜、オランダ海軍提督のヤコブ・ロッゲフェーンが、南太平洋上に浮かぶ小さな島を発見する。発見した日がイースター のため「イースター島」と名前が付いたと言われている。この島に上陸したロッゲフェーンは、1000体を超えるモアイと、その前で火を焚 き地に頭を着けて、祈りを捧げる島人の姿を目の当たりにする。1774年には、イギリス人探検家のジェームス・クックも上陸している。 クックが目にしたものは、倒れ壊されたモアイ像の数々で、島のモアイの半数ほどが、まだ直立していたと云う。そして山肌には作りかけ のモアイ像が、まるで作業を急に止めてしまったかのように放置されていた。伝承では1840年に最後のモアイが倒されたとされる。 18世 紀〜19世紀にかけてペルー政府の依頼を受けたアイルランド人のジョセフ・バーンや、タヒチのフランス人の手によって、住民らが奴隷と して連れ出された。また外部から持ち込まれた天然痘が猛威を振るった。その結果島の人口は更に激減し、先住民は絶滅寸前まで追い込ま れた。1872年当時の島民数はわずか111人である。1888年にチリ領になり現在に至る。 <文 字> 住民はポリネシアで唯一文字を持っていた。ラパヌイ文字(ロンゴロンゴ文字)と呼ばれる絵文字がこれに当たる。この絵文字は古代文字 によく見られる牛耕式と呼ばれる方法で書かれ、1行目を読み終えると逆さにして2行目を読むというように、偶数行の絵文字が逆さになっ ている。板や石に書かれ、かつては木材に刻まれたものが多数存在したようである。宣教師らが「悪魔の文字」であるとして破壊したとい う俗説があるが、実際は過度の伐採により木材が常に不足している島の住民たちによって、薪や釣り糸のリールとなり、多数の文字資料が 失われたという。そのため、現在はわずか26点しか存在しない。また、現在のラパ・ヌイ人は、フランス人の奴隷狩りによりタヒチに連れ 去られ、戻ってきた人々の子孫であり、現行のラパ・ヌイ語はタヒチ語の影響を強く受けた言語である。古代ラパ・ヌイ語についてはヨー ロッパ人による貧弱な記録をたどる他は、現行のラパ・ヌイ語から復元する以外、知る手立ては存在しない。したがって、解読は難しいと されている。 ラパヌイ文字はインダス文字との外見上の類似を指摘されている。ただ、現存する資料は全て西洋人との接触後に書かれたものと見られて いる。ラパ・ヌイの先住民が最初に外国から来た船で西洋人と接した時、文字の存在を知り、その有効性を学び、そこから自らの文字を真 似て作り上げたとする説も極めて有力である。そのため、ラパヌイ文字をポリネシアの古来からの書記言語と断定することはできない。 よって、インダス文字との関わりについては、学術的には、あくまでも一つの可能性という範囲に留まっている。



<オセアニア諸国> ・独立国 オーストラリア連邦 クック諸島(ニュージーランドと自由連合) フィジー共和国 ミクロネシア連邦 キリバス共和国 マーシャル諸島共和国 ナウル共和国 ニュージーランド パプアニューギニア独立国 パラオ共和国 ソロモン諸島 トンガ王国 ツバル バヌアツ共和国 サモア独立国 ・主な各国領 米領サモア(アメリカ準州) ココス (キーリング) 諸島(オーストラリア領) クリスマス島(オーストラリア領) グアム(アメリカ準州) パプア州・西パプア 北マリアナ諸島(アメリカ自治領) ニューカレドニア(フランス領) ノーフォーク島(オーストラリア領) ニウエ(ニュージーランドと自由連合) 仏領ポリネシア(フランス海外領邦) ピトケアン諸島(イギリス領) トケラウ諸島(ニュージーランド領) ハワイ州(アメリカ合衆国州) ウォリス=フツナ(フランス領) ウェーク島(アメリカ領有) ジョンストン環礁(アメリカ領有) ミッドウェー環礁(アメリカ領有)オセアニア全体の面積は約850万km2である。 <海面上昇> 地球温暖化に伴う海面上昇は、海抜の低い小島嶼国家の存立に深刻な影響を与える。 IPCC(気候変動に関する政府間パネル、 Intergovermental Panel on Climate Change)の報告書はミクロネシアのマーシャル諸島共和国について、環礁の約8割が海面下になる可 能性を警告している。 <地域機構> アジア太平洋経済協力 太平洋共同体 太平洋諸島フォーラム 南太平洋委員会
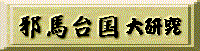 邪馬台国大研究/博物館めぐり/みんぱく
邪馬台国大研究/博物館めぐり/みんぱく