 Music: 赤い靴
Music: 赤い靴
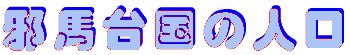
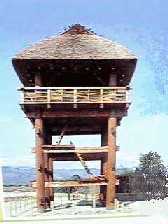
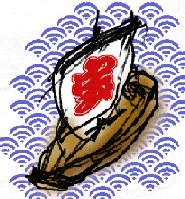
我が国古代の人口問題については、多くの先人達による研究が残されている。
近代科学としての人口学でその業績が際だっているのは、数学者で歴史学者(東京帝大の物理学科と国史学科を卒業)
でもあった沢田吾一(1861〜1931)である。今日でも、古代人口学において彼の研究を越える研究は現れていない。
幾つかの問題点は内包しているが、彼の研究は現在でも、古代史における人口問題(邪馬台国時代から奈良時代、特
に奈良時代について。)を研究する際の基本となっている。
沢田吾一氏の研究
沢田氏の取った方法は次のようなものであった。①、古文書等を基に、奈良時代の行政単位である郷の平均人口を推
定算出し、これを @1,399人 とした。②、これに和名抄の郷数 4,041 を
掛け全国総人口を560万とした。③、更に、この数に賤民、雑民、私民の数等を加え奈良時代の全国総人口を 600万人
〜700万人と推定した。
沢田氏は國別郷別の人口も算出しているがここでは割愛する。沢田氏の算出したこの数字は、今日でも概算値として
よく用いられているが、現在の研究成果ではやや少な目である、という事になっている。
沢田氏の算出した数字から、邪馬台国の主な比定地である大和地方と筑前・筑後地方の数字だけを拾い出すと以下の
ようになる。(延長5年(AD.927年)頃の値)
| 國名 | 推定人口(人) | 郷数 | 郷別人口(人) |
| 大和 | 130,300 | 89 | 1,464 |
| 筑前 | 89,150 | 102 | 874 |
| 筑後 | 74,300 | 54 | 1,376 |
魏志倭人伝には、邪馬台国の人口は残されていないが7万戸という戸数は書き残している。古代の家族構成が一戸
あたり何人であったのか判然としないが、極々少な目に見積もっても4〜5人は居たであろう。今日でも発掘され
続けている古代遺跡(縄文晩期から弥生時代中期)の状況からすると、私の考えではおそらく一戸あたりの人口は
10人〜15人ではないかと思うのだが、これだと70万人〜105万人という事になり、これは今日でも大都会
の人口である。少な目の4〜5人で計算しても28〜35万人となり、これでもまだ大都市の人口であろう。
先述の沢田氏の人口計算と照らし合わせてみても、奈良にも筑紫にもこれだけの人口は存在しない。筑前・筑後を
合わせても16万3千人にすぎない。では一体どういう事になるのか?
①、魏志はいい加減に戸数を記録したのか?
②、奈良/筑紫にほんとはもっと沢山の人が居たのか? 或いは、
③、もっと人口の多い、奈良でもなく筑紫でもなく、第三の有力候補地が存在するのか?
答えは、わからないである。今日では、①、②、③、のそれぞれの見解に立った説が百花繚乱である。推理作家
であり古代史にも造詣の深かった松本清張氏は、① の立場であった。即ち、7万戸というのはあまりに多すぎる、
中国では三、五、七という数字はいわばゴロあわせのように用いるのであって、ここで言う7万戸という数字も実
際はもっと少なかったに違いない、と言う。安本美典氏は、筑前・筑後に肥前(今の佐賀県)の有明海沿岸の人口
も加算して7万戸であろう、とする。いずれにしても、魏の使いが一体どういう基準で7万戸を割り出したのか、
明確に答えられた者は居ないのである。
現在の人口学は、沢田氏のとった方法よりもっと科学的である。
桑原秀夫氏(1869〜1997:日本数学史学会、近畿数学史学会会員)は、古代人口の推計方法として次の3つを挙げ
ている。
①、地理学的方法 ②,考古学的方法 ③,人口学的方法である。①は、地域面積とその単位人口からある地域、或い
は日本全体の総人口を計算しようとするもので、②は、古代の住居跡の遺物から計算する方法、③は、現在の人口
状態から推移して古代の人口を求めようとするもの、である。桑原氏は数学者の視点から、数式モデルを用い ③
の方法で考察している。桑原氏も奈良期の人口を6〜7百万人としているが、邪馬台国には言及していない。
人口問題では、古代現代を問わず今日でも沢山の研究が進行中である。我が国古代の書物による人口記載の分析か
ら、電算機を用いた数式モデルのシミュレーションによるものなど方法は様々だが、今もって多くの研究者が真理に迫ろう
と努力を続けている。幾つかの参考文献を以下に記す。
願わくば新たなる学究の徒が出現せん事を祈りたいものである。
人口学研究参考文献
●福本誠・『筑前誌』・1903国光社(昭和49年に臨川書店から復刻)
●末永茂世編・『筑前旧志略』・明治20年刊行
●沢田吾一・『奈良朝時代民族経済の数的研究』・昭和2年富書房
●古屋芳雄・『日本民族混成誌』・1944日新書院
●本庄栄治郎・『日本人口史』・昭和16年
●舘稔・『形式人口学』・昭和35年
●賀川光夫・『この当時の家族構成はどの程度までわかるのか』・昭和49年日本書籍刊「日本考古学の視点」
●文化庁・『全国遺跡地図』・1965文化庁
●高橋梵仙・『日本人口史之研究』・1971学振
●関山直太郎・『日本の人口』・昭和41年至文堂
●板倉聖宣・『歴史の見方考え方』・仮説社
●斉藤忠・『日本考古学の視点 上』・1974日本書籍
●藤岡健次郎編・『日本歴史地理総説 古代編』・1975吉川弘文館
●鬼頭宏・『日本二千年の人口史』・PHP研究所「二十一世紀図書館」
●小山修三・『縄文時代』・1984中公新書
●穴沢和光・『古代文化』・1984/10月号
●植原和朗・『骨から古墳人を推理する』・1986中央公論社刊「日本の古代5 前方後円墳の世紀」
●他
 邪馬台国大研究・ホームページ / INOUES.NET / 邪馬台国の人口
邪馬台国大研究・ホームページ / INOUES.NET / 邪馬台国の人口 

 Music: 赤い靴
Music: 赤い靴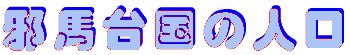
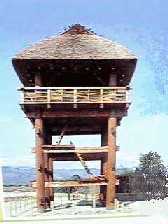
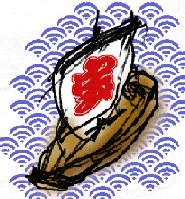
 邪馬台国大研究・ホームページ / INOUES.NET / 邪馬台国の人口
邪馬台国大研究・ホームページ / INOUES.NET / 邪馬台国の人口 
